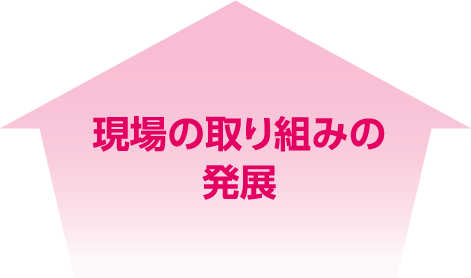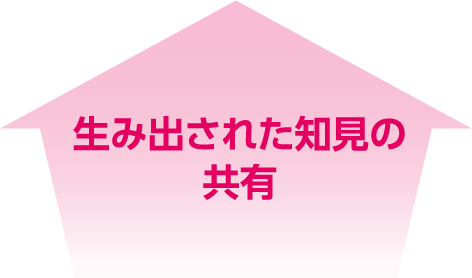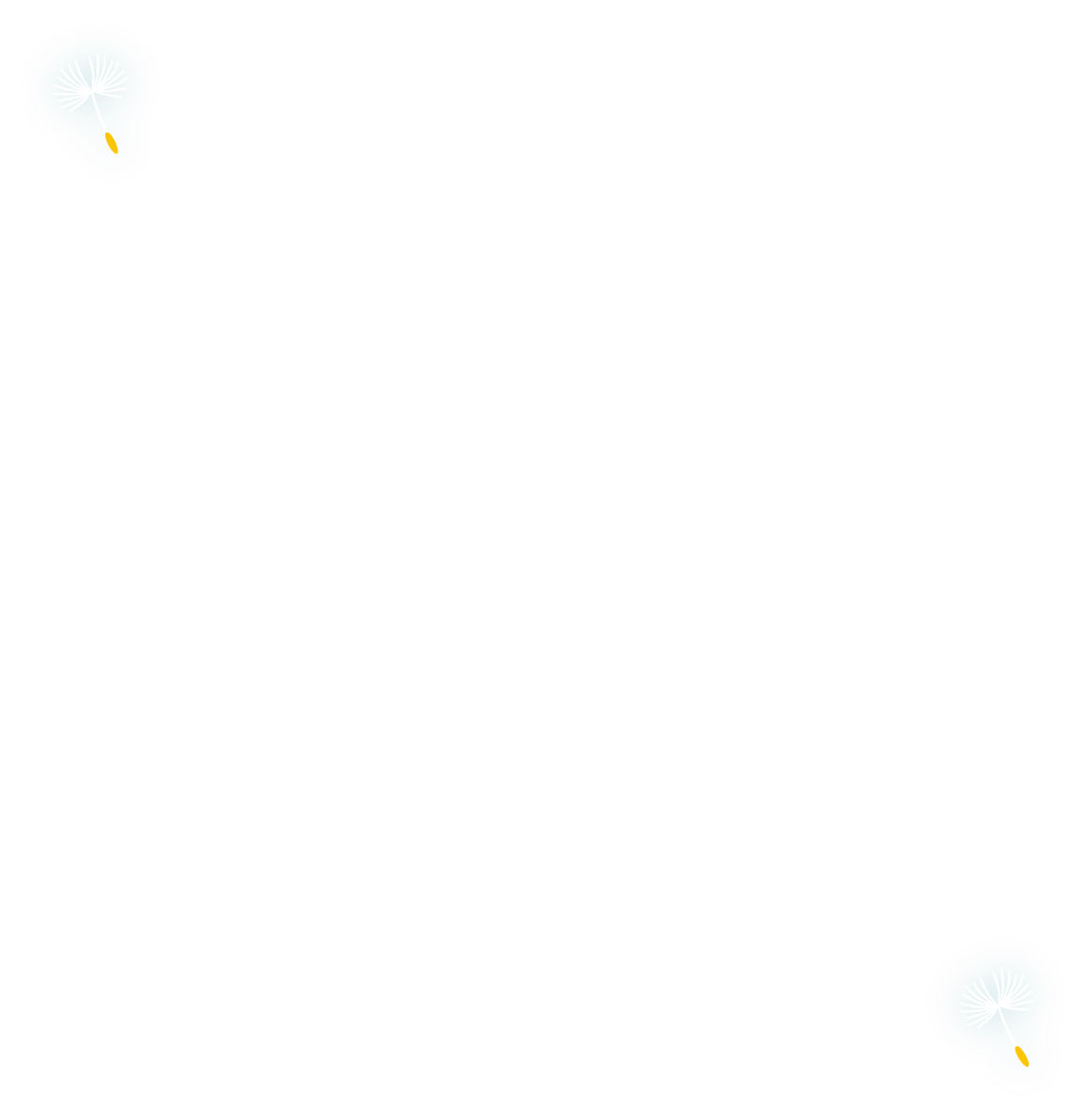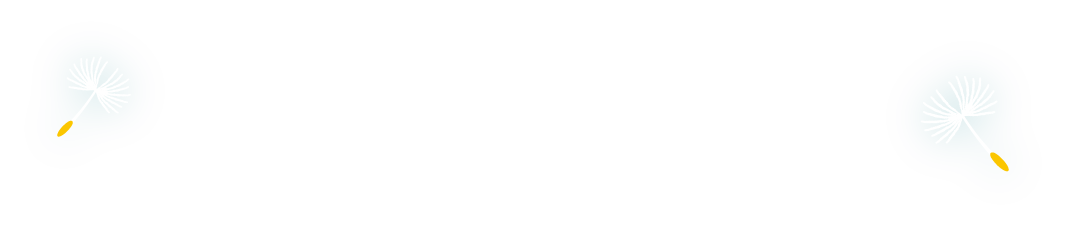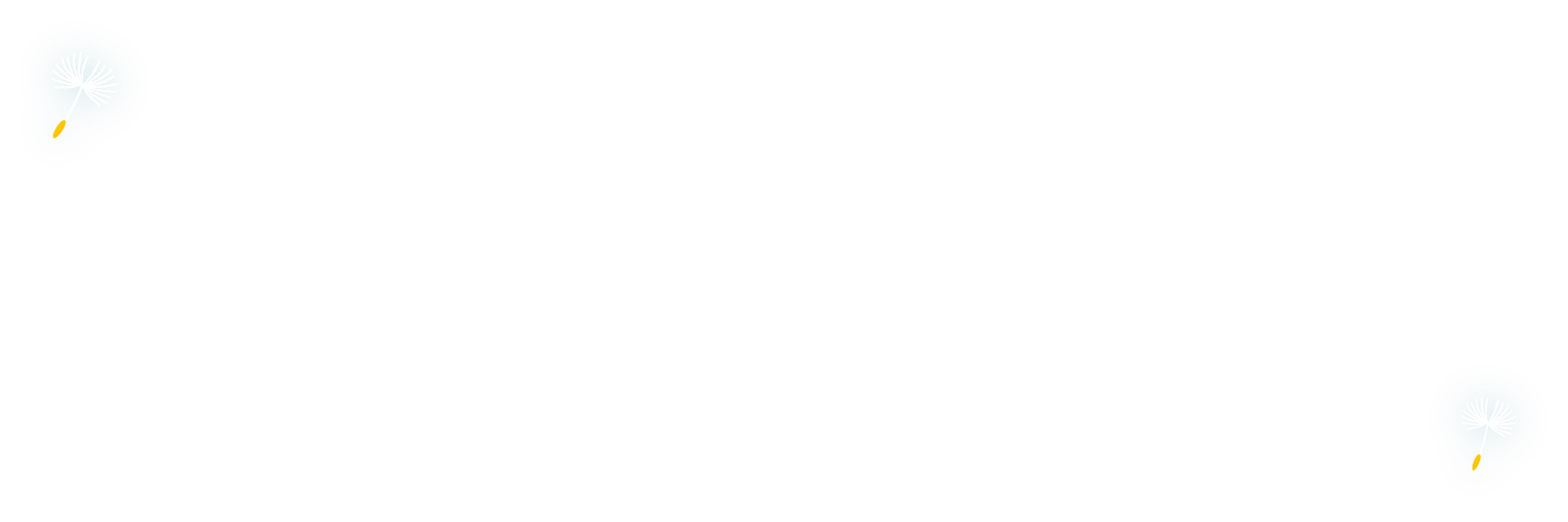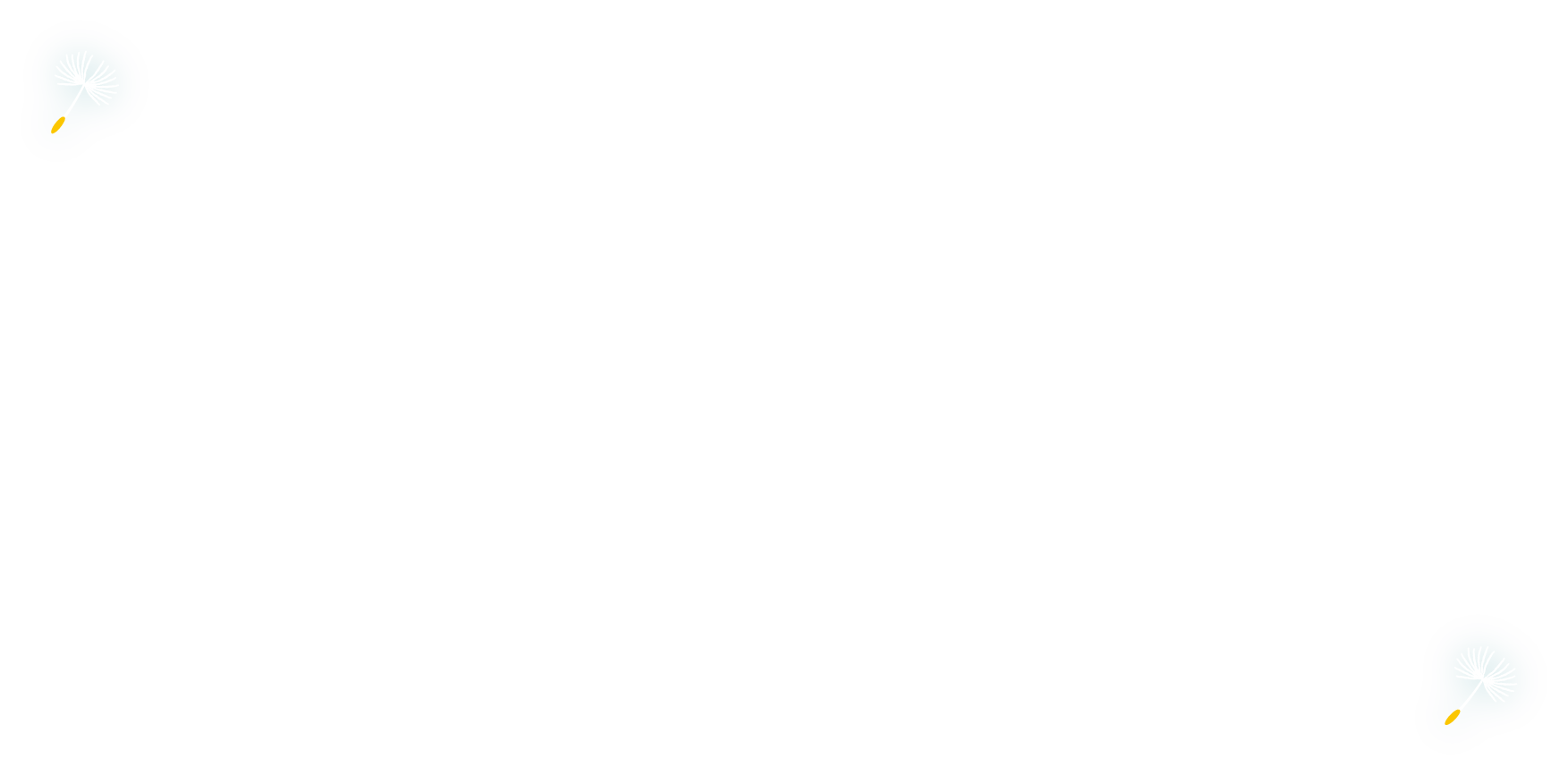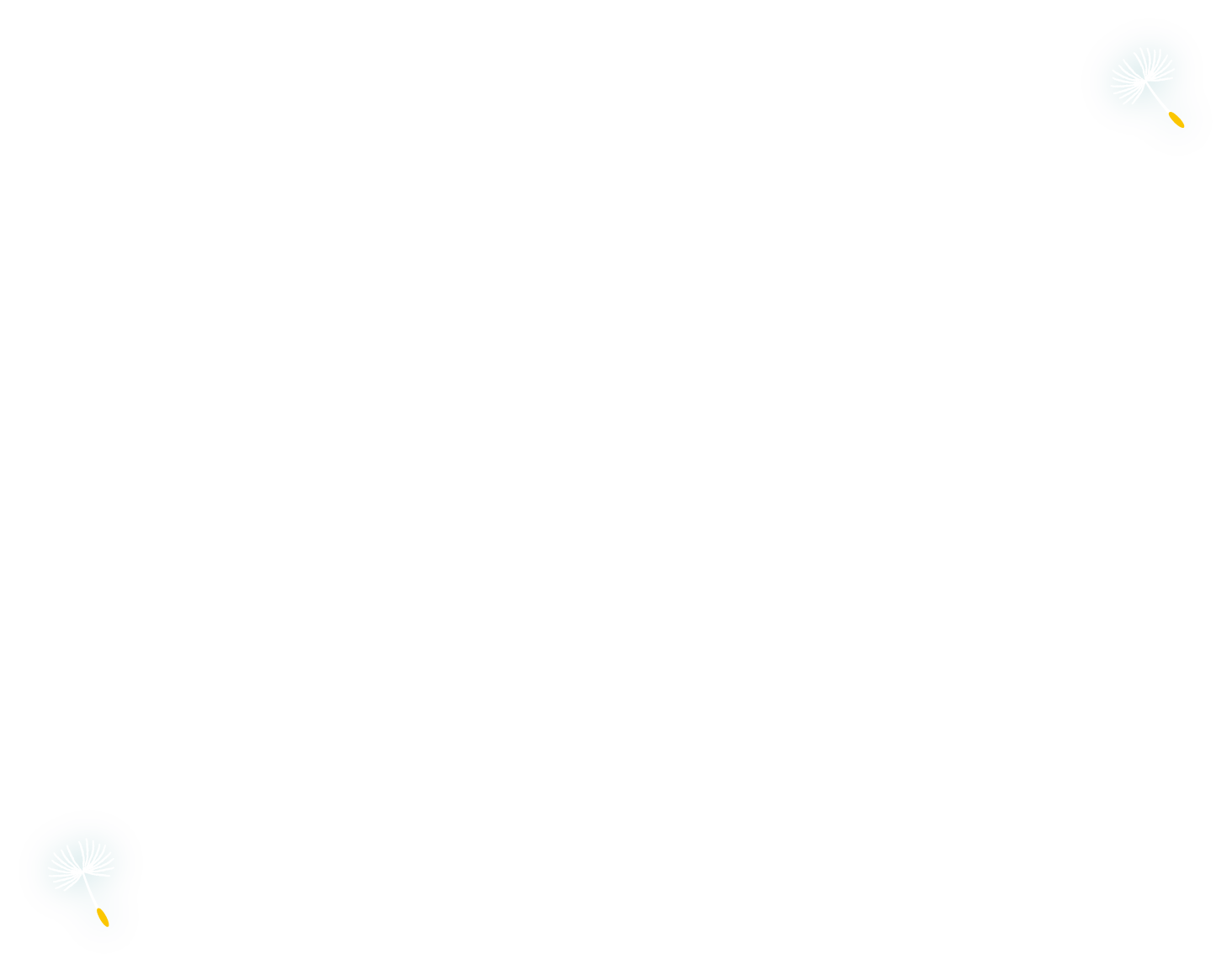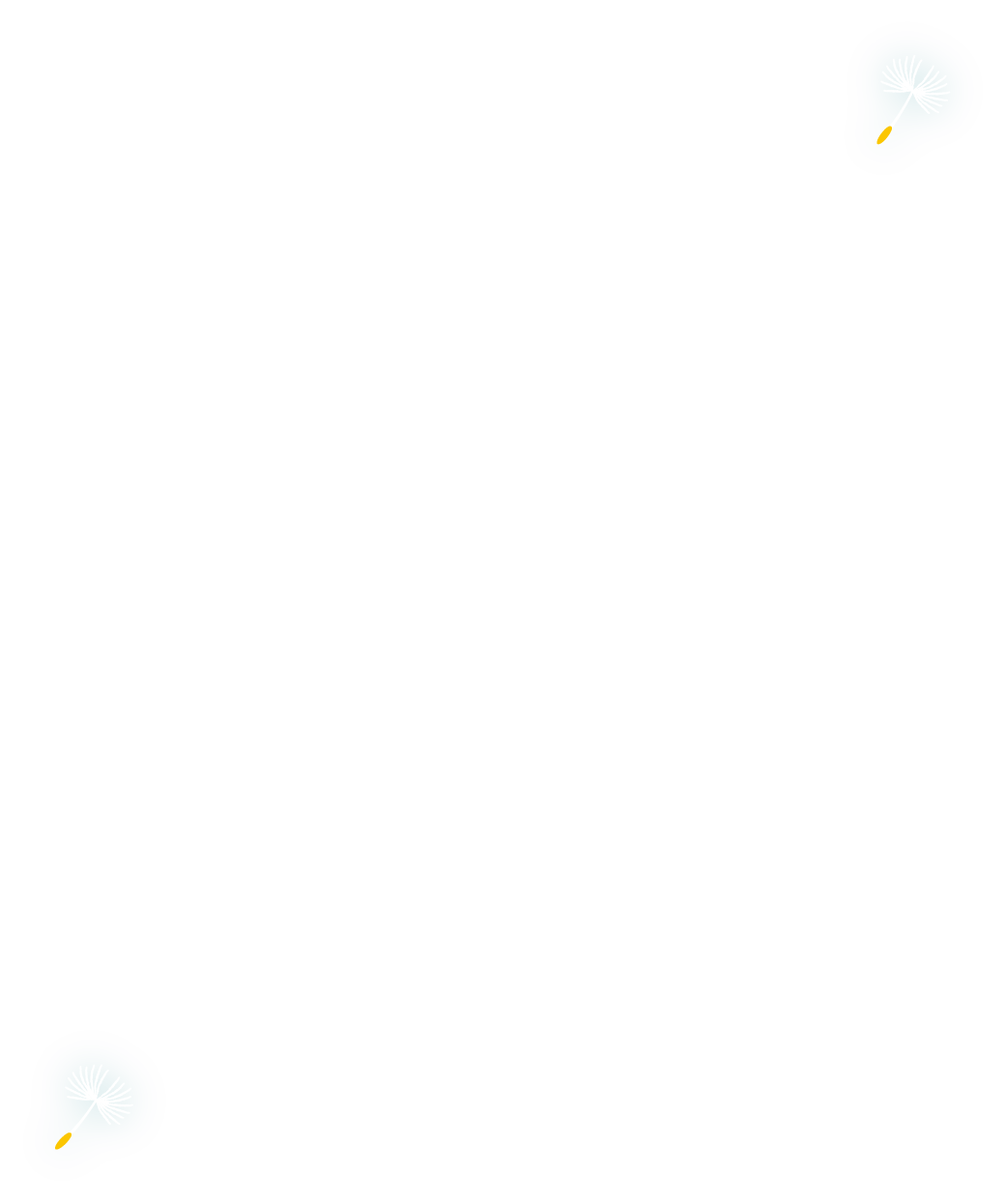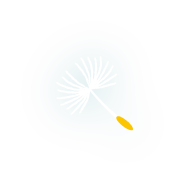JANPIAが目指す社会
JANPIAが目指す社会
JANPIAは、「誰ひとり取り残さない持続可能な社会づくりへの触媒」として、休眠預金活用事業に取り組む皆さまと共に、
「目指す社会」の実現に向けて、取り組んでいきます。
目指す社会
これまで社会課題一般に認識されていないために対応が遅れている分野、公的制度のはざまに取り残された課題、そして新たに生まれる課題。これらの課題を置き去りにすることなく、多様な人々が担い手として共に支えあい、一人ひとりの生活や地域の環境をよくするために動く。
そのように動く人や組織が増えることで、「課題が解決され続ける社会」へと着実に近づいていけると、JANPIAは考えます。
休眠預金活用事業は、その目指す社会へ向かう、一つの力となります。
休眠預金活用事業から
生み出される価値(事業の成果)
休眠預金活用事業から生み出される3つの価値が相互に繋がり、民間公益活動が持続的に発展することで、「目指す社会」へ向かう力となります。
- 社会課題解決をめざす現場の取り組みが、事業を通じて「課題解決力」や「組織基盤」を強化することで、持続可能性を高めさらに発展します
- 分野の垣根を超えて様々な立場の関係者の連携を促進し、現場の活動を支える地域や分野の「中間支援機能」を持つ組織がさらに発展します
- 休眠預金活用事業を通じて生み出された知見や経験が広く共有・活用されることで、社会からの共感・信頼を得て、現場と中間支援機能の更なる発展につながります
休眠預金活用事業
(私たちが取り組むこと)
行政では対応することが難しい社会課題を解決するため、公募で選ばれた民間の団体(資金分配団体・活動支援団体、実行団体・支援対象団体)が、3分野に休眠預金等を活用しています。
JANPIAは休眠預金等活用に関わる全てのステークホルダーとの連携・協働、そしてそれを実現するための徹底した対話を通じ、同じ志をもって進む団体と共に、この事業の持続的発展を目指し、積極的に活動を進めます。
休眠預金等活用制度において指定活用団体としての役割を担うJANPIAは、休眠預金活用事業に取り組む関係者とともに、目指すべき世界観を共有するためのツールとして、様々なステークホルダーとの議論を重ね、この「JANPIAが目指す社会」を作成しました。 これを議論のベースとし、今後も実践と検討を重ねたいと考えています。